2023年06月07日
ありがとうFA-MAS
東京マルイの元祖電動ガン、FA-MASがカタログ落ちした、らしい。
いつのまにかひっそりと消えていた様だけど、ツイッターで話題になって知った次第。
考えてみれば発売以来30年経っているし、ホップが追加されたりのアップデートはあったものの、モーターは初期から唯一560を使い続けているし、外装も今のレベルで見ると気の毒と言える物で、終了自体はやむなし、と言うかむしろ今まで残っていた事が奇跡とも言える。
とは言え、発売当時予約してまで購入、以後の電動ガンと共に戦った自分のサバゲ人生(笑)を振り返ると、やはり感慨深い物がある訳です。
FA-MAS発売前後、自分のように熱烈に待望してたサバゲーマーは少なからず居ましたが、まだまだパワー重視、今で言う「暗黒極悪パワー時代」(この認識にも異論はありますが)であった当時、マルイの評価は「安物エアガンメーカー」であり、発表時の予想は「電動のチャチなやつ」「安っぽくてすぐ壊れる」「使い物になる筈が無い」が大勢で
既存製品の「でも命中精度が異様に良いんだよ」と言う点から期待を寄せる意見は少数派でした。
発売されてみると、意外と内部メカは金属多用で思ったよりしっかり作られ、パワーも「既製のエアガン並」にはあるし、良く当るのもあって「初心者にはアリだろ」的な扱いにはなりました。
当時のハイエンド製品だったアサヒ製ガスガンやフルチューンしたスーパー9のユーザー等の「ガチ勢」からは当然相手にもされず。
ただ、当時は既に行き過ぎたパワー競争を問題視して比較的低威力で遊ぼう、と言うグループもそれなりに存在し、トイテックやマルゼン等、比較的低威力で性能の良い製品も受け入れられている、と言う、それなりにプラス要因も有りました。
「強化スプリング」等のカスタムパーツは割とすぐに発売されましたが、これはそれ以前に存在した「KG9」等のエアガン用と寸法がほぼ一緒だったから。
極初期はそれらの在庫品の転用でした。
それでも、電動ガンがガスガンを駆逐してしまう程とは想像もつかず、「電動ガンの天下」を築くのは後のM16、MP5シリーズの登場以降となります。
マルイFA-MASの人生は、記念すべき電動ガンの元祖にして始祖、の割には意外と華々しくはなかったんだよなぁ。
ユニットも単発で兄弟や後継機種がなかったし。
ともあれ、マルイFA-MAS君、お疲れ様。
出来れば次世代とかに生まれ変わって・・・・って、実銃の方の不人気っぷりから考えたら無いだろうなぁ。
いつのまにかひっそりと消えていた様だけど、ツイッターで話題になって知った次第。
考えてみれば発売以来30年経っているし、ホップが追加されたりのアップデートはあったものの、モーターは初期から唯一560を使い続けているし、外装も今のレベルで見ると気の毒と言える物で、終了自体はやむなし、と言うかむしろ今まで残っていた事が奇跡とも言える。
とは言え、発売当時予約してまで購入、以後の電動ガンと共に戦った自分のサバゲ人生(笑)を振り返ると、やはり感慨深い物がある訳です。
FA-MAS発売前後、自分のように熱烈に待望してたサバゲーマーは少なからず居ましたが、まだまだパワー重視、今で言う「暗黒極悪パワー時代」(この認識にも異論はありますが)であった当時、マルイの評価は「安物エアガンメーカー」であり、発表時の予想は「電動のチャチなやつ」「安っぽくてすぐ壊れる」「使い物になる筈が無い」が大勢で
既存製品の「でも命中精度が異様に良いんだよ」と言う点から期待を寄せる意見は少数派でした。
発売されてみると、意外と内部メカは金属多用で思ったよりしっかり作られ、パワーも「既製のエアガン並」にはあるし、良く当るのもあって「初心者にはアリだろ」的な扱いにはなりました。
当時のハイエンド製品だったアサヒ製ガスガンやフルチューンしたスーパー9のユーザー等の「ガチ勢」からは当然相手にもされず。
ただ、当時は既に行き過ぎたパワー競争を問題視して比較的低威力で遊ぼう、と言うグループもそれなりに存在し、トイテックやマルゼン等、比較的低威力で性能の良い製品も受け入れられている、と言う、それなりにプラス要因も有りました。
「強化スプリング」等のカスタムパーツは割とすぐに発売されましたが、これはそれ以前に存在した「KG9」等のエアガン用と寸法がほぼ一緒だったから。
極初期はそれらの在庫品の転用でした。
それでも、電動ガンがガスガンを駆逐してしまう程とは想像もつかず、「電動ガンの天下」を築くのは後のM16、MP5シリーズの登場以降となります。
マルイFA-MASの人生は、記念すべき電動ガンの元祖にして始祖、の割には意外と華々しくはなかったんだよなぁ。
ユニットも単発で兄弟や後継機種がなかったし。
ともあれ、マルイFA-MAS君、お疲れ様。
出来れば次世代とかに生まれ変わって・・・・って、実銃の方の不人気っぷりから考えたら無いだろうなぁ。
2013年11月25日
おっさんゲーマーの回想録(7)
今ではインターネットが普及して、家に居ながら情報集めや会ったこともない相手と趣味の話題で繋がれるのが当たり前になっていますが、それ以前、ゲーム開催や仲間集め、エアガンやカスタムのノウハウ等の情報をどうやって得ていたか想像出来るでしょうか?
俺がサバゲを始めた頃はインターネットどころか携帯電話も無く、学生の俺のアパートには電話すら有りませんでした(笑)
情報は、自分の足で外に出掛けて行かなければ得られなかったのです。
学校や職場での仲間あつめや情報交換、口コミでの広がりはもちろん大きかったです。
俺も迷彩服を着て専門学校の教室で声掛けられて仲間が出来たりしましたし。
専門誌はそれなりの役割は果たしていました。
記事の内容は先に述べた自主規制の都合がありヘビーユーザー殆どあてにしてませんでしたが、新製品情報等は得られましたし、記事の行間から実状を察するみたいな楽しみ(?)も無くはなかったのです。
広告に関しては規制の影響が少ない場合もあったので、参考になる事もありました。
ゲーム情報に関しては、当時の雑誌には読者交流コーナーみたいな物があって、「隊員募集」や「対戦相手募集」が沢山載ってました。
全国誌に実名と住所を晒す、と言う今から考えると個人情報もへったくれもないトンデモな方法ではありますが、当時は利用者も多かった様に思います。
サバゲ黎明期には、既に結構大規模なチームが存在していました。
と言うのも、サバゲが流行る以前からモデルガンを使った撃ち合いや戦争ゴッコのチームが既に存在していたからです。
現在で言うリエクナメント、ヒストリカルゲームに近い集まりもあり、サバゲ黎明期にはそれらのチームの多くがエアガンに転向、あるいは平行して参加していたのです。
サバゲのルーツが「ペイントボールゲーム」であると言われつつ、日本では独自の進化をしてミリタリーテイストが強くなったのは、この影響が大きいでしょう。
エアガンが実銃のデザインを忠実に再現する様になったのも、エアガン独自の進化をするよりも、それら既存のモデルガンマニアにアピールする方が商売として成り立ち易かったのです。
当時は町の玩具屋や模型店等を含め、エアガンを扱ってる小さなシヨップが結構あちこちにあり、そこで集まったり実際にゲームフィールドで知り合ったりと言う具合にネットワークも広がっていました。
通販は既にかなり発達していましたが、エアガン全般に製品としての成熟度が低かった事もあり、現物を見て確認して買うと言う需要は今より高く、小規模でも知識がある小売店の存在意義は今より大きかったのです。
「〇〇〇のカスタムが凄い」と評判になれば、直接見に行ったり、実際に買ったり、そして分解してみたり。
今より情報量が少ない分、フットワークが軽かったような気がします。
チューンナップノウハウに関する情報源としては、これらの小売店に商品を供給する問屋の役割も大きく、新しいカスタムパーツが出れば商品情報として発信されましたし、ゲームでの評判は店を通してフィードバックされたり共有されたりしていた物です。
とはいえ、エアガンの性能はゲームでの優位性を左右する事もあるので、お店や仲間内で発見、開発した技術を秘密にしているケースも勿論ありました。
しかし、世に出た物が長く秘密に出来る物ではありません(笑)
当時も今もマニアと言うのは情報に貪欲でしたから、有効な物は大抵暴かれて広まったと思われます。
解りやすい例はホップアップバレル等でしょうか。
逆に広まらなかった「秘密兵器」と言うのはそれほど大した物では無かったと言う事ですが、怪しげな噂だけが都市伝説のように広まったりする事もありました。
それらの都市伝説の幾つかは、今でも当時のエピソードの「実話」として耳にする事もあります。
1990年代に入る頃には、エアガンの製品としての完成度は高くなり、専門知識やノウハウを持ったショップの需要は減りました。
電動ガンの登場により、その傾向は強まります。
折しも大手家電量販店が玩具、プラモデルの売り場を拡張してエアガンの取り扱いを始め、中小のショップは販売価格で勝負が出来ず次々廃業して行きます。
最悪だったのは、その後エアガン絡みの事件が多発したり、地方条例強化の煽りを受けて、量販店が扱いを縮小したり取り止めてしまった事です。
ショップを中心にしたネットワークは小さな仲間内のグループごとに分断され、ゲームの開催が難しくなるケースも少なからず。
また、社会的な目も厳しくなり、川原や空き地、公園等でやっていたゲームは開催不可能になって行きます・・・・って、今の感覚では当然でしょうが、当時はまだまだ、おおらかな時代だったのです(笑)
インターネット普及したり、千葉県に次々と専用フィールドがオープンする以前のこの時代こそが、別の意味で「暗黒時代」と呼ぶに相応しいように思います。
さてさて、おっさんの昔ばなしもボチボチクドくなりすぎたんで終わりにしましょうか~。
結論として、「昔は良かった」とかそんな事は全然無く、今は夢のように素晴らしいよって言っておきます。
今の状況が当たり前に元からそうだった訳じゃ無いし、不満や要望はもちろん、それぞれ有るだろうけど、これからずっと変わらない訳でもない、と知って貰えれば良いですね。
俺がサバゲを始めた頃はインターネットどころか携帯電話も無く、学生の俺のアパートには電話すら有りませんでした(笑)
情報は、自分の足で外に出掛けて行かなければ得られなかったのです。
学校や職場での仲間あつめや情報交換、口コミでの広がりはもちろん大きかったです。
俺も迷彩服を着て専門学校の教室で声掛けられて仲間が出来たりしましたし。
専門誌はそれなりの役割は果たしていました。
記事の内容は先に述べた自主規制の都合がありヘビーユーザー殆どあてにしてませんでしたが、新製品情報等は得られましたし、記事の行間から実状を察するみたいな楽しみ(?)も無くはなかったのです。
広告に関しては規制の影響が少ない場合もあったので、参考になる事もありました。
ゲーム情報に関しては、当時の雑誌には読者交流コーナーみたいな物があって、「隊員募集」や「対戦相手募集」が沢山載ってました。
全国誌に実名と住所を晒す、と言う今から考えると個人情報もへったくれもないトンデモな方法ではありますが、当時は利用者も多かった様に思います。
サバゲ黎明期には、既に結構大規模なチームが存在していました。
と言うのも、サバゲが流行る以前からモデルガンを使った撃ち合いや戦争ゴッコのチームが既に存在していたからです。
現在で言うリエクナメント、ヒストリカルゲームに近い集まりもあり、サバゲ黎明期にはそれらのチームの多くがエアガンに転向、あるいは平行して参加していたのです。
サバゲのルーツが「ペイントボールゲーム」であると言われつつ、日本では独自の進化をしてミリタリーテイストが強くなったのは、この影響が大きいでしょう。
エアガンが実銃のデザインを忠実に再現する様になったのも、エアガン独自の進化をするよりも、それら既存のモデルガンマニアにアピールする方が商売として成り立ち易かったのです。
当時は町の玩具屋や模型店等を含め、エアガンを扱ってる小さなシヨップが結構あちこちにあり、そこで集まったり実際にゲームフィールドで知り合ったりと言う具合にネットワークも広がっていました。
通販は既にかなり発達していましたが、エアガン全般に製品としての成熟度が低かった事もあり、現物を見て確認して買うと言う需要は今より高く、小規模でも知識がある小売店の存在意義は今より大きかったのです。
「〇〇〇のカスタムが凄い」と評判になれば、直接見に行ったり、実際に買ったり、そして分解してみたり。
今より情報量が少ない分、フットワークが軽かったような気がします。
チューンナップノウハウに関する情報源としては、これらの小売店に商品を供給する問屋の役割も大きく、新しいカスタムパーツが出れば商品情報として発信されましたし、ゲームでの評判は店を通してフィードバックされたり共有されたりしていた物です。
とはいえ、エアガンの性能はゲームでの優位性を左右する事もあるので、お店や仲間内で発見、開発した技術を秘密にしているケースも勿論ありました。
しかし、世に出た物が長く秘密に出来る物ではありません(笑)
当時も今もマニアと言うのは情報に貪欲でしたから、有効な物は大抵暴かれて広まったと思われます。
解りやすい例はホップアップバレル等でしょうか。
逆に広まらなかった「秘密兵器」と言うのはそれほど大した物では無かったと言う事ですが、怪しげな噂だけが都市伝説のように広まったりする事もありました。
それらの都市伝説の幾つかは、今でも当時のエピソードの「実話」として耳にする事もあります。
1990年代に入る頃には、エアガンの製品としての完成度は高くなり、専門知識やノウハウを持ったショップの需要は減りました。
電動ガンの登場により、その傾向は強まります。
折しも大手家電量販店が玩具、プラモデルの売り場を拡張してエアガンの取り扱いを始め、中小のショップは販売価格で勝負が出来ず次々廃業して行きます。
最悪だったのは、その後エアガン絡みの事件が多発したり、地方条例強化の煽りを受けて、量販店が扱いを縮小したり取り止めてしまった事です。
ショップを中心にしたネットワークは小さな仲間内のグループごとに分断され、ゲームの開催が難しくなるケースも少なからず。
また、社会的な目も厳しくなり、川原や空き地、公園等でやっていたゲームは開催不可能になって行きます・・・・って、今の感覚では当然でしょうが、当時はまだまだ、おおらかな時代だったのです(笑)
インターネット普及したり、千葉県に次々と専用フィールドがオープンする以前のこの時代こそが、別の意味で「暗黒時代」と呼ぶに相応しいように思います。
さてさて、おっさんの昔ばなしもボチボチクドくなりすぎたんで終わりにしましょうか~。
結論として、「昔は良かった」とかそんな事は全然無く、今は夢のように素晴らしいよって言っておきます。
今の状況が当たり前に元からそうだった訳じゃ無いし、不満や要望はもちろん、それぞれ有るだろうけど、これからずっと変わらない訳でもない、と知って貰えれば良いですね。
2013年11月12日
おっさんゲーマーの回想録(6)
このシリーズもいい加減長くなってしまったのだけど、書いてる内に思い出した事等もあり、もう少し続けようかと思います。
まずはゲームでの使用BB弾について。
発売された最初のBB弾は恐らくマルゼン製品で、エアガンの箱に同梱されている物と同じ、プラスチックの箱に納められていました。
確か100発400円位だったと記憶があります。
結構な値段でしたが、ケース式コッキングエアガンしかない頃にはまあそれほど気にはしませんでした。
使ったって一日二箱程度、むしろカートリッジを無くす方が痛い損害でしたから(笑)
しかし、ケースレスレピーターカスタムが主流になって行くと、使用弾数が増えるのでコストが気になり出します。
俺が上京した1986年頃には、各社からBB弾が発売され値段も下がりました。
記憶にあるのはマルシンのSMブルーBBとか、MGCのスーパーグレッツとか。
サンエイのBB弾が発売されたのもこの頃だったような・・・。
およそ一発あたり1~2円が相場だったでしょうか。
数千発入りの大袋と言うのはまだあまり無く、1000円ぐらいで数百発入ってるような物が多かったですね。
メーカー製BB弾は供給が悪く、店頭で在庫が切れている事も度々で、恐らくサバゲでバリバリ撃ちまくる用途は想定外だったのでしょう。
アフターサービスの一環程度の認識であったのかもしれません。
そんな状況ですから、弾を選ぶと言う様な選択肢はあまりなく、入手可能な物を手当たり次第に買って使っていました。
同じ頃、0.2g以上の重量弾も登場します。
今は無き模型メーカーのLSが、0.27gとかの弾を発売したりもしました。
他にも数種類有ったと思いますが、あまり印象に残ってません・・・・・・。
しかし、そのすぐ後に当時唯一の業界団体でエアガン製造メーカーの組合であったASGKが、自主規制を打ち出して、0.2g以上の弾はメーカーからは発売出来なくなりました。
この為、重量弾は入手困難になるのか・・・と心配する間もなく、ASGKに加盟していないデジコン電子が超重量弾を含め、製品を供給し始め、一気に普及する事になります。
最近のエアガンファンにとっては、「デジコン」と言えば極悪パワーの代名詞、凶悪なエアガンを製造していたアングラメーカーと言う印象かもしれませんが、実はかなり長い間サバゲで使われるBB弾は、0.2gから超重量弾まで、デジコン製品にほぼ独占されていました。
当時のASGKの業界での影響力は大きく、自主規制と言えどもかなりの強制力を持っていました。
自主規制に沿わない物は一般流通に乗せられず、専門誌で広告を打つ事も、記事に載せる事すら出来なかったのです。
ガスガン普及以前に、既に超重量弾の需要はあり、デジコン弾は口コミで広がりました。
問屋が扱わない(表向きは、ですが)分、専門店への直卸しで販路を確保していた様です。
ガスガンが普及すると、BV式が軽い弾ではまともに集弾しない事から、0.3gくらいの弾が当たり前に使われていたと思います。
それ以上の重さの弾となると金額的な問題でフルオートでの使用はあまり無かったと思いますが、セミオートやコッキングエアガンは対抗上、重量弾で精度を上げる傾向にあったようです。
後に半額ぐらいに値下げにはなりますが発売当初のデジコン超重量BB弾は0.36gが1000発3600円、0.43gが4300円。
0.2gは1000円ぐらいでしたから、いかにバブル全盛の頃だったとは言え、超重量弾はやはり高いと感じた物でした。
もう一つ、極悪ハイパワーの象徴的に言われる貝殻弾については、実はデジコン製品が出回る以前から存在する、ほぼ唯一の超重量弾でした。
元々が養殖真珠の核の、ちょうど良い物を選定してるだけでBB弾ですらないのですが、重くて滑りが良くパワーと集弾性を得られる秘密兵器的扱い。
しかし、メッシュゴーグルで割れて破片が中に入る事があり危険と言う事で禁止しているケースも多かったと思います。
禁止しなくても超重量弾に比べてさえ更に高額。
確か100個で800円位だったと思うのですが、選別すると半分くらいは使えない、と言う超高級品で、とてもバラ撒ける物では無かったのです。
デジコン超重量弾が出てからは、ほぼ見かけなくなりました。
フルオート時代には既に過去の物だったのですが、そのプレミアム性故か「伝説の弾」的な扱いでした。
ついでに書いて置くと、スチールベアリングは超重量級の弾の更に倍の重さがありますので、発射可能ではあっても威力はむしろ落ちますし、まともに飛びませんのでサバゲで使ったと言う例はいくらなんでも殆ど無い筈ですね。
一般的に0.2g弾がゲームの標準になって行くのは、ASCSの影響もありますが、トイテック製品の普及も影響大だったと思います。
同社が当時としては激安で高い精度の0.2g弾を販売した事で一気に重量弾との価格差が開いた為だと思われます。
電動ガンの多弾マガジンが当たり前の現在からは想像が難しいでしょうが、トイテック登場以前のフルオートガスガンでは1マガジンの装弾数は多くて100発ぐらいが相場でした。
BV式は構造上マガジンにも圧力がかかり、気密を取らなければならないため、多弾化が難しかったのです。
カスタム手法としては多弾化の方法もあったのですが、「カエルの卵」と揶揄される様に外観が崩れ、性能も落ちるので嫌う人も多く、メーカーが純正として採用するのは難しかったのです。
アサヒ製品では、後に新型ユニットのブッシュマスター、FNC用の300連ドラムマガジンが少数発売されましたが、これは同社のこれらの製品がエア給弾方式だったから例外的に可能だった事です。
そんな中、新興メーカーだったトイテックが装弾数1000発のキャリコを突然発表したのですから、衝撃的でした。
雑談に広告が載った時には有り得ない程の低価格もあって目を疑い、新手のサギかと疑った位でした(笑)
トイテックのガスガンの利点は先にも述べましたが、その利点を最大限に生かす為には安価なBB弾は不可欠でした。
安価なだけの弾は当時もありましたが、トイテックのユニットは精巧な給弾システムを持っていたので、弾の精度も必要です。
そのへんメーカーさんは良く判っていたので、当時の0.2g弾としては破格の、1000発500円の格安高精度弾を発売したのです。
メーカー製BB弾としては供給も良く、他メーカーの追従もあり弾の値段は大幅に下がりました。
低圧ゲームの普及と共に重量弾使用は減り、逆に多弾数化による消費量増大に拍車がかかりました。
一時代を支えたデジコンBB弾も価格面で勝負にならなくなり、重量弾の需要も頭打ち。
恐らくこの頃、売り上げが落ちていたのではないでしょうか?
デジコンは自社製品のガスガンを発売したりしましたが、その路線は次第に極端なパワー志向に傾いて行きます。
この頃、ASGKも規制を見直し、0.2g以上の弾も認められる様になったのですが、このへんの前後関係がイマイチ記憶が曖昧です(汗)
もう1つの業界団体あるJASGが発足したのは少し後だった筈ですが、こちらは規制値が最初からASGKよりかなり高めです。
1990年代半ばぐらいには、「1J、0.2g」というレギュレーションが普及し始め、超重量段は精密射撃系のみに使用されるようになって行ったのですが、流速チューンの流行で近年、再びサバゲに戻って来ました。
個人的には昔から「弾の重量に関わらず想定される最大の危険は至近距離での被弾なのだから、威力を低く抑えれば問題ない」と言う主張なのですが、よく被弾する5m以上の距離では明らかに痛いのも事実なので、重量弾規制もある程度仕方が無いなあ、とも思います。
規制値の話のついでですが、ASGKの自主規制値は良く知られている通り「0.4J」なんですが、この数値、0.2g弾で初速およそ60m/sです。
どのくらいの威力かと言うと、マルイのいわゆる1900円シリーズがだいたいそのくらいです。
こう書くと大体想像つくと思いますが、当初から殆ど守られていませんでした。
極悪パワー時代故に、ユーザーの要求でハイパワー化されて有名無実になった訳ではありません。
売ってる状態では0.6~0.8Jくらいの物が多かったように思います。
ようするに、今と殆ど変わらない威力ですな。
ただ、ホップシステムは搭載されていなかったので、物足りなさはありましたが。
5mくらいで明らかに落ちる弾道では「もう少しパワーがあれば・・・」と思ってしまうのも無理のない話です。
現在はASGKも「競技用」と言う名目で0.8Jまで規制値を緩めましたが、ようするに現状追認ですな。
過去の規制が厳しすぎたんだと言わざるを得ません。
ASGKの影響力が大きい頃、雑誌の新製品紹介の記事は広告主を喜ばせる為になんとか良く書こうとしつつ、ユーザーは強力な物を欲しがるし、かと言って自主規制値を越える数値を書く訳にも行かず、と言った事情があり、随分苦労をしていた様子が記事からも伺えます。
対して当時のゲーマーの多くは、雑誌の記事は実際とかけ離れすぎているのを知っていたので全くアテにしてませんでした。
ネットも無い時代、専門誌に載って残っている情報が実はかなり実情と離れていたと言う事は意外と知られていなくて、当時の様子が見え難くなっている事が「暗黒時代」等と言われてしまう一因なのではないかと思う訳です。
まずはゲームでの使用BB弾について。
発売された最初のBB弾は恐らくマルゼン製品で、エアガンの箱に同梱されている物と同じ、プラスチックの箱に納められていました。
確か100発400円位だったと記憶があります。
結構な値段でしたが、ケース式コッキングエアガンしかない頃にはまあそれほど気にはしませんでした。
使ったって一日二箱程度、むしろカートリッジを無くす方が痛い損害でしたから(笑)
しかし、ケースレスレピーターカスタムが主流になって行くと、使用弾数が増えるのでコストが気になり出します。
俺が上京した1986年頃には、各社からBB弾が発売され値段も下がりました。
記憶にあるのはマルシンのSMブルーBBとか、MGCのスーパーグレッツとか。
サンエイのBB弾が発売されたのもこの頃だったような・・・。
およそ一発あたり1~2円が相場だったでしょうか。
数千発入りの大袋と言うのはまだあまり無く、1000円ぐらいで数百発入ってるような物が多かったですね。
メーカー製BB弾は供給が悪く、店頭で在庫が切れている事も度々で、恐らくサバゲでバリバリ撃ちまくる用途は想定外だったのでしょう。
アフターサービスの一環程度の認識であったのかもしれません。
そんな状況ですから、弾を選ぶと言う様な選択肢はあまりなく、入手可能な物を手当たり次第に買って使っていました。
同じ頃、0.2g以上の重量弾も登場します。
今は無き模型メーカーのLSが、0.27gとかの弾を発売したりもしました。
他にも数種類有ったと思いますが、あまり印象に残ってません・・・・・・。
しかし、そのすぐ後に当時唯一の業界団体でエアガン製造メーカーの組合であったASGKが、自主規制を打ち出して、0.2g以上の弾はメーカーからは発売出来なくなりました。
この為、重量弾は入手困難になるのか・・・と心配する間もなく、ASGKに加盟していないデジコン電子が超重量弾を含め、製品を供給し始め、一気に普及する事になります。
最近のエアガンファンにとっては、「デジコン」と言えば極悪パワーの代名詞、凶悪なエアガンを製造していたアングラメーカーと言う印象かもしれませんが、実はかなり長い間サバゲで使われるBB弾は、0.2gから超重量弾まで、デジコン製品にほぼ独占されていました。
当時のASGKの業界での影響力は大きく、自主規制と言えどもかなりの強制力を持っていました。
自主規制に沿わない物は一般流通に乗せられず、専門誌で広告を打つ事も、記事に載せる事すら出来なかったのです。
ガスガン普及以前に、既に超重量弾の需要はあり、デジコン弾は口コミで広がりました。
問屋が扱わない(表向きは、ですが)分、専門店への直卸しで販路を確保していた様です。
ガスガンが普及すると、BV式が軽い弾ではまともに集弾しない事から、0.3gくらいの弾が当たり前に使われていたと思います。
それ以上の重さの弾となると金額的な問題でフルオートでの使用はあまり無かったと思いますが、セミオートやコッキングエアガンは対抗上、重量弾で精度を上げる傾向にあったようです。
後に半額ぐらいに値下げにはなりますが発売当初のデジコン超重量BB弾は0.36gが1000発3600円、0.43gが4300円。
0.2gは1000円ぐらいでしたから、いかにバブル全盛の頃だったとは言え、超重量弾はやはり高いと感じた物でした。
もう一つ、極悪ハイパワーの象徴的に言われる貝殻弾については、実はデジコン製品が出回る以前から存在する、ほぼ唯一の超重量弾でした。
元々が養殖真珠の核の、ちょうど良い物を選定してるだけでBB弾ですらないのですが、重くて滑りが良くパワーと集弾性を得られる秘密兵器的扱い。
しかし、メッシュゴーグルで割れて破片が中に入る事があり危険と言う事で禁止しているケースも多かったと思います。
禁止しなくても超重量弾に比べてさえ更に高額。
確か100個で800円位だったと思うのですが、選別すると半分くらいは使えない、と言う超高級品で、とてもバラ撒ける物では無かったのです。
デジコン超重量弾が出てからは、ほぼ見かけなくなりました。
フルオート時代には既に過去の物だったのですが、そのプレミアム性故か「伝説の弾」的な扱いでした。
ついでに書いて置くと、スチールベアリングは超重量級の弾の更に倍の重さがありますので、発射可能ではあっても威力はむしろ落ちますし、まともに飛びませんのでサバゲで使ったと言う例はいくらなんでも殆ど無い筈ですね。
一般的に0.2g弾がゲームの標準になって行くのは、ASCSの影響もありますが、トイテック製品の普及も影響大だったと思います。
同社が当時としては激安で高い精度の0.2g弾を販売した事で一気に重量弾との価格差が開いた為だと思われます。
電動ガンの多弾マガジンが当たり前の現在からは想像が難しいでしょうが、トイテック登場以前のフルオートガスガンでは1マガジンの装弾数は多くて100発ぐらいが相場でした。
BV式は構造上マガジンにも圧力がかかり、気密を取らなければならないため、多弾化が難しかったのです。
カスタム手法としては多弾化の方法もあったのですが、「カエルの卵」と揶揄される様に外観が崩れ、性能も落ちるので嫌う人も多く、メーカーが純正として採用するのは難しかったのです。
アサヒ製品では、後に新型ユニットのブッシュマスター、FNC用の300連ドラムマガジンが少数発売されましたが、これは同社のこれらの製品がエア給弾方式だったから例外的に可能だった事です。
そんな中、新興メーカーだったトイテックが装弾数1000発のキャリコを突然発表したのですから、衝撃的でした。
雑談に広告が載った時には有り得ない程の低価格もあって目を疑い、新手のサギかと疑った位でした(笑)
トイテックのガスガンの利点は先にも述べましたが、その利点を最大限に生かす為には安価なBB弾は不可欠でした。
安価なだけの弾は当時もありましたが、トイテックのユニットは精巧な給弾システムを持っていたので、弾の精度も必要です。
そのへんメーカーさんは良く判っていたので、当時の0.2g弾としては破格の、1000発500円の格安高精度弾を発売したのです。
メーカー製BB弾としては供給も良く、他メーカーの追従もあり弾の値段は大幅に下がりました。
低圧ゲームの普及と共に重量弾使用は減り、逆に多弾数化による消費量増大に拍車がかかりました。
一時代を支えたデジコンBB弾も価格面で勝負にならなくなり、重量弾の需要も頭打ち。
恐らくこの頃、売り上げが落ちていたのではないでしょうか?
デジコンは自社製品のガスガンを発売したりしましたが、その路線は次第に極端なパワー志向に傾いて行きます。
この頃、ASGKも規制を見直し、0.2g以上の弾も認められる様になったのですが、このへんの前後関係がイマイチ記憶が曖昧です(汗)
もう1つの業界団体あるJASGが発足したのは少し後だった筈ですが、こちらは規制値が最初からASGKよりかなり高めです。
1990年代半ばぐらいには、「1J、0.2g」というレギュレーションが普及し始め、超重量段は精密射撃系のみに使用されるようになって行ったのですが、流速チューンの流行で近年、再びサバゲに戻って来ました。
個人的には昔から「弾の重量に関わらず想定される最大の危険は至近距離での被弾なのだから、威力を低く抑えれば問題ない」と言う主張なのですが、よく被弾する5m以上の距離では明らかに痛いのも事実なので、重量弾規制もある程度仕方が無いなあ、とも思います。
規制値の話のついでですが、ASGKの自主規制値は良く知られている通り「0.4J」なんですが、この数値、0.2g弾で初速およそ60m/sです。
どのくらいの威力かと言うと、マルイのいわゆる1900円シリーズがだいたいそのくらいです。
こう書くと大体想像つくと思いますが、当初から殆ど守られていませんでした。
極悪パワー時代故に、ユーザーの要求でハイパワー化されて有名無実になった訳ではありません。
売ってる状態では0.6~0.8Jくらいの物が多かったように思います。
ようするに、今と殆ど変わらない威力ですな。
ただ、ホップシステムは搭載されていなかったので、物足りなさはありましたが。
5mくらいで明らかに落ちる弾道では「もう少しパワーがあれば・・・」と思ってしまうのも無理のない話です。
現在はASGKも「競技用」と言う名目で0.8Jまで規制値を緩めましたが、ようするに現状追認ですな。
過去の規制が厳しすぎたんだと言わざるを得ません。
ASGKの影響力が大きい頃、雑誌の新製品紹介の記事は広告主を喜ばせる為になんとか良く書こうとしつつ、ユーザーは強力な物を欲しがるし、かと言って自主規制値を越える数値を書く訳にも行かず、と言った事情があり、随分苦労をしていた様子が記事からも伺えます。
対して当時のゲーマーの多くは、雑誌の記事は実際とかけ離れすぎているのを知っていたので全くアテにしてませんでした。
ネットも無い時代、専門誌に載って残っている情報が実はかなり実情と離れていたと言う事は意外と知られていなくて、当時の様子が見え難くなっている事が「暗黒時代」等と言われてしまう一因なのではないかと思う訳です。
2013年11月09日
おっさんゲーマーの回想録(5)
電動ガン登場の1991年当時、確かに極悪パワーはまだ存在していましたし、威力の弱い電動ガンは当初「子供のオモチャ」的な見方をする人達も居ました。
とは言うものの、初期には低圧レギュレーションのゲームが既にある程度定着しており、ガスガンと電動ガンはしばらく共存していました。
高圧、高威力ゲームも続いてはいましたが、かなりコアな人達のみで、ゲームでの主流は法規制より遥かに早く、電動ガンが主流になる頃には現在の1Jに近いレギュレーションに落ち着いていた所が多かったと思われます。
ここでもう一冊の本。

アームズマガジン別冊で、1992年刊行です。
アームズマガジン主催のゲーム大会、ASCS(確か、第4回目?)の紹介があります。
1989年に始まった夏のサバゲ大会で、当初からかなり低威力のレギュレーションを採用していました。
0.2gBB弾まで、と言うのも特徴的で、第1回大会当時はまだBV式全盛期。
レギュレーションも含め、突飛すぎると受け取られ「お遊び」と揶揄すらされましたが、この時期になると逆に低威力ゲームがある程度浸透しつつありました。
ASCSが低威力ゲーム定着に与えた影響は大きいと思います。
記事を見ると電動MP5とM16が発売となる時期ですが、大会時には確か未発売だった筈。
写真から大会の様子を伺うとガスガンとの混合ぶりが見て取れます。

電動ガンユーザーが圧倒的に多くなったのは、M16シリーズが発売されてからでしょう。
幾らか下火になったとは言え、まだベトナム戦争装備は人気がありましたし、「タンクやホースが邪魔だった」と言う装備系の人達にも好評でした。
戦闘中にバックパックを背負ったまま、と言うのはある意味「リアルでは無い」ですから(笑)
第一弾のFA-MAS比べると人気も知名度も比べ物になりません。
電動ガン登場当初から、ガスガンに比べてやはり威力が弱い事もあり、電動ガンのチューニングは盛んでした。
主に強化スプリングと、気密性向上等、強力なバネを引き切るための駆動系チューニング、ホップバレルに関しても、固定バレルのエアガンとの相性が良い事は比較的良く知られていたので、あっと言う間もなく従来のカスタムパーツの転用で何社からも出ました。
耐久性能向上のためのギアやピストンもすぐに発売されました。
初期には電動ガンは無制限とされる場合が多かったのですが、当時のレギュレーションを上回る事も可能ではありました。
しかし、電動ガンが壊れない、無理のないカスタムで遊べる様にと、積極的にレギュレーションを適用し、引き下げたケースが多かった様に記憶しています。
更に純正可変ホップ搭載は決定的でした。
先の本にもホップアップの解説があり、この当時感心が高かった事が伺えます。
電動ガンやトイテックのガスガン等はバレル固定式で元々集弾性能が良く、ホップとの相性が良かった事もあり、アフターパーツでのホップバレルは人気がありました。

マルイ純正ポップアップは、それらアフターパーツを全て過去の物にしてしまう圧倒的性能だったので、低圧対応したガスガンでは、射程距離で全く歯が立たなくなってしまったのです。
低威力のゲームでは、ガスガン+エアタンクは殆ど見かけなくなりました。
エアタンク使用者が激減すると、煩わしいタンク充填用のコンプレッサーの運用が無くなり、コンプレッサーが無いとエアタンク使用者はほぼ完全に居なくなりました。
有料フィールドの草分けであるSPL(現SPF)やIBF、SASがオープンする頃には、既にコンプレッサーを用意する程の需要は殆ど無くなっていた様です。
当時まだ存在していた高圧レギュレーションのゲームに対して批判的に「極悪パワー」と言う言葉が良く使われる様になり、行き過ぎたパワー競争に対する反動もあった為か、外部ソース使用そのものに拒否感を示す人が多くなり、結果、多くのゲームで外部ソースの使用すら禁止という雰囲気にさえなりました。
当時、低威力ゲームを普及させたい人達にとっては、高圧、高威力でなければ満足に撃ち合いが出来なかった過去を払拭したい気持ちはありました。
そんな意図もあり、差別的な意味で使われた「極悪パワー」と言う言葉が、後にその時代全てを指して「黒歴史」とまで言われる様になる・・・・
何とも皮肉な物です。
現在の低威力でのゲームは、多くのゲーマーがそう望んだからそうなったのであって、決して外的要因でそうさせられた結果では無いのです。
強力なエアガンが使われた時代も、サバゲ成立の過程であって、「黒歴史」等と称して触れない様にするのは間違っていると思います。
話は飛びますが、現在の法規制の数値は当時のサバゲでの使用の実情に配慮された結果であると思われます。
恐らく水面下では多くの方の尽力もあったのではないかとも推測されますが、かつてのモデルガン規制の時の「趣味」と言う物への無理解と容赦無い法規制に比べると、雲泥の差であると思えるのです。
幸いにして今は楽しく健全にサバゲが出来るし、専用フィールドも沢山あり、ちょっとしたブームと言っても良い様子ですが、それが未来永劫不変で続いて当たり前では無いよ、と言う事はちょっと意識してほしいですねー。
と、一応締めて見ましたが、まだちょっと続けるつもりです。
とは言うものの、初期には低圧レギュレーションのゲームが既にある程度定着しており、ガスガンと電動ガンはしばらく共存していました。
高圧、高威力ゲームも続いてはいましたが、かなりコアな人達のみで、ゲームでの主流は法規制より遥かに早く、電動ガンが主流になる頃には現在の1Jに近いレギュレーションに落ち着いていた所が多かったと思われます。
ここでもう一冊の本。

アームズマガジン別冊で、1992年刊行です。
アームズマガジン主催のゲーム大会、ASCS(確か、第4回目?)の紹介があります。
1989年に始まった夏のサバゲ大会で、当初からかなり低威力のレギュレーションを採用していました。
0.2gBB弾まで、と言うのも特徴的で、第1回大会当時はまだBV式全盛期。
レギュレーションも含め、突飛すぎると受け取られ「お遊び」と揶揄すらされましたが、この時期になると逆に低威力ゲームがある程度浸透しつつありました。
ASCSが低威力ゲーム定着に与えた影響は大きいと思います。
記事を見ると電動MP5とM16が発売となる時期ですが、大会時には確か未発売だった筈。
写真から大会の様子を伺うとガスガンとの混合ぶりが見て取れます。

電動ガンユーザーが圧倒的に多くなったのは、M16シリーズが発売されてからでしょう。
幾らか下火になったとは言え、まだベトナム戦争装備は人気がありましたし、「タンクやホースが邪魔だった」と言う装備系の人達にも好評でした。
戦闘中にバックパックを背負ったまま、と言うのはある意味「リアルでは無い」ですから(笑)
第一弾のFA-MAS比べると人気も知名度も比べ物になりません。
電動ガン登場当初から、ガスガンに比べてやはり威力が弱い事もあり、電動ガンのチューニングは盛んでした。
主に強化スプリングと、気密性向上等、強力なバネを引き切るための駆動系チューニング、ホップバレルに関しても、固定バレルのエアガンとの相性が良い事は比較的良く知られていたので、あっと言う間もなく従来のカスタムパーツの転用で何社からも出ました。
耐久性能向上のためのギアやピストンもすぐに発売されました。
初期には電動ガンは無制限とされる場合が多かったのですが、当時のレギュレーションを上回る事も可能ではありました。
しかし、電動ガンが壊れない、無理のないカスタムで遊べる様にと、積極的にレギュレーションを適用し、引き下げたケースが多かった様に記憶しています。
更に純正可変ホップ搭載は決定的でした。
先の本にもホップアップの解説があり、この当時感心が高かった事が伺えます。
電動ガンやトイテックのガスガン等はバレル固定式で元々集弾性能が良く、ホップとの相性が良かった事もあり、アフターパーツでのホップバレルは人気がありました。

マルイ純正ポップアップは、それらアフターパーツを全て過去の物にしてしまう圧倒的性能だったので、低圧対応したガスガンでは、射程距離で全く歯が立たなくなってしまったのです。
低威力のゲームでは、ガスガン+エアタンクは殆ど見かけなくなりました。
エアタンク使用者が激減すると、煩わしいタンク充填用のコンプレッサーの運用が無くなり、コンプレッサーが無いとエアタンク使用者はほぼ完全に居なくなりました。
有料フィールドの草分けであるSPL(現SPF)やIBF、SASがオープンする頃には、既にコンプレッサーを用意する程の需要は殆ど無くなっていた様です。
当時まだ存在していた高圧レギュレーションのゲームに対して批判的に「極悪パワー」と言う言葉が良く使われる様になり、行き過ぎたパワー競争に対する反動もあった為か、外部ソース使用そのものに拒否感を示す人が多くなり、結果、多くのゲームで外部ソースの使用すら禁止という雰囲気にさえなりました。
当時、低威力ゲームを普及させたい人達にとっては、高圧、高威力でなければ満足に撃ち合いが出来なかった過去を払拭したい気持ちはありました。
そんな意図もあり、差別的な意味で使われた「極悪パワー」と言う言葉が、後にその時代全てを指して「黒歴史」とまで言われる様になる・・・・
何とも皮肉な物です。
現在の低威力でのゲームは、多くのゲーマーがそう望んだからそうなったのであって、決して外的要因でそうさせられた結果では無いのです。
強力なエアガンが使われた時代も、サバゲ成立の過程であって、「黒歴史」等と称して触れない様にするのは間違っていると思います。
話は飛びますが、現在の法規制の数値は当時のサバゲでの使用の実情に配慮された結果であると思われます。
恐らく水面下では多くの方の尽力もあったのではないかとも推測されますが、かつてのモデルガン規制の時の「趣味」と言う物への無理解と容赦無い法規制に比べると、雲泥の差であると思えるのです。
幸いにして今は楽しく健全にサバゲが出来るし、専用フィールドも沢山あり、ちょっとしたブームと言っても良い様子ですが、それが未来永劫不変で続いて当たり前では無いよ、と言う事はちょっと意識してほしいですねー。
と、一応締めて見ましたが、まだちょっと続けるつもりです。
2013年11月06日
おっさんゲーマーの回想録(4)
エアタンクの登場はフルオートガスガン登場から割とすぐの事で、ホームセンター等で売っている自動車用のエアホーンのタンクを持ち込む人が現れたのが最初でした。
しばらくしてニッケンのエアガン専用品も発売され、普及したのはJACの大ヒット作となるUZI発売以降であったと思います。
高価なフロンガスを垂れ流しに使うブースターシステムは温度低下で使い物にならず不評で、ランニングコストの安いエアホーンタンクにフルオートガスガンユーザーは皆飛び付きました。
しかしエアホーンタンクは当然ですが、入っている圧力が直結でそのまま出てくると言う代物です。
圧力規制の最初はレギュレーターのないエアホーン用タンクの直結を規制する意味で8気圧位の規制でした。
今から考えると確かにとんでもない圧力ですが、まあ、初期のフルオートガスガンなんて、ガス垂れ流しでたいした性能では無かったんですけどね。
ましてや直結の場合、撃てば撃つほど圧力は下がり威力もサイクルも落ちる訳ですし、圧力が安定しない状態ではセッティングもへったくれもあったものではありません。
極悪ハイパワーの象徴のように言われるJACやアサヒのBV式ガスガン(当時はそんな呼び方は一般的では無かったですけど、以後便利なのでこの表記を使います)ですが、エアタンク登場当初は、それほど恐れられてはいませんでした。
最も脅威だったのはコクサイのセミオートM16。
外観は先代スーパーウェポン使い回しながら、唯一のM16の実用的ガスガンでした。
当時としては命中精度が高く、スナイパーライフルとしても割と長い期間活躍した隠れた名銃であります。
他にも、MGC93R等やWAのAR7等。
当初はフルオートの為に使用されたであろうエアタンクは、高圧で安定した高い威力を発揮できるので、セミオートガスガンにも使用されました。
SS9に比べても圧力次第では簡単に強力に出来るので恐れらる様になり、エアタンク登場当初に、むしろ高威力で槍玉に上げられる事が多かったのはこちらの方だったのです。
恐らく、当時としてはSS9系と公平に同等の威力にしようと言う事で8気圧ぐらいと決めたのではなかったかと思います。
当初は圧力を落とす為の可変レギュレーターは高価な為、取り付けに反発もありましたが、レギュレーター装着した方が安定した性能が出せると言う事で結局あっと言う間に普及します。
と言うか、フルオートガスガンはレギュレーター付きになってようやく、まともな性能になったと言っても良い位です。
その後エアガン用タンクとして発売されたニッケンのタンクは固定レギュレーターが標準装備されていたのですが、可変レギュレーターに交換したり、レギュレーターの圧力が高くなるように改造するのは当たり前のように行われていました。
先行して普及していたのが可変レギュレーターで、高圧設定であったので、それに合わせる為ですが、当時のフルオートガスガンはメーカー出荷状態の出来が悪く、製品のバラツキもあって箱出しで低圧作動が出来ない物が結構あったのも、これらの改造を当初から否定出来なかった理由の一つでした。
JAC、アサヒのBV式ガスガンは正常作動には5気圧以上必要だった物が多く、圧力規制は長く5~6気圧が下限だった気がします。
また、箱出しのできの悪さ故に適正にチューニングした物との性能差が大きく、チューニングノウハウの有無による格差も問題でした。
実際、撃ち合って威力が違い過ぎるので、「レギュレーションを守っていないんだろう」と言う疑心暗鬼が生まれ、チェックが甘い事もあり安易に圧力を上げる人も居たようです。
このへんの事情が現在に続く、「外部ソース=インチキし易い」のイメージ定着につながったのではないかと思います。
少し後の話にはなりますが、後発で低価格商品だったマルゼンの製品のほうが、同じBV式ガスガンながら低圧ではむしろ最初から調子が良いと言う事もあり、低圧縛りのゲームでは多く見かけました。
低予算でサバゲが始められるので低圧ゲームは新規参加者も少なくはなかったと思います。
逆に高圧縛りだと、どうしても高級品を揃えなければ厳しいし、エア消費量も多いのでエアタンクもより大容量の物が必要、(スキューバ用タンクを流用するケースもありました)エア充填にも時間がかかりゲーム数が少なくなりがち、と言う事でコアな人達しか居なくなり、人数を減らして行きました。
話は少し横道に反れますが、エアタンク登場当初は個人で空気入れを持参、エア充填するのが当たり前だったのですか、インターバルに人力で空気を入れるのはゲーム以上に重労働、時間もかかりました。
1日で4ゲームしか出来なかった、なんて事もあった程です。
後にチーム単位や主催者がエンジンコンプレッサー等を持ち込むケースが多く見られる様になりましたが、エアタンク使用者が増えると充填待ちに時間を取られる様になり、やはりインターバルが長くなりがちになりました。
待ち時間が長くなるのは嫌だ、ゲーム数を増やしたいと言う参加者の希望もあり、インターバルを短縮する必要からエアの消費を抑える為、レギュレーションで圧力を低くする事が受け入れられ易かった、と言う側面もある様に思います。
外部ソースガスガンでのゲームも末期になると、トイテックのキャリコやP90等、高圧対応やパワーアップが難しい銃も登場してきます。
それまでフルオートガスガンの主流だったBV式に比べて多弾化され、低圧で安定した作動、ガス消費が少ない、値段も安かった等々メリットもありましたが、低圧レギュレーションがある程度普及していなければ受け入れられ、使用者が増える事は無かったでしょう。
BVガスガンの「リコイル」と言うのに相応しい反動と派手な発射音の愛好家は根強く存在しましたし、強力なエアガンでスリルを楽しむと言う趣向の人達も確かに居ました。
自然発生、寄り合いでゲームが開催されていた所がほとんどだったという事情でレギュレーションの不徹底、あるいは無制限に近いゲームは2008年の法規制施行まで存在してはいましたが、1990年頃、電動ガン登場の頃には低圧、低威力のレギュレーションでのゲームがある程度定着していた様に思います。
くどいですけど、まだ続きます。
しばらくしてニッケンのエアガン専用品も発売され、普及したのはJACの大ヒット作となるUZI発売以降であったと思います。
高価なフロンガスを垂れ流しに使うブースターシステムは温度低下で使い物にならず不評で、ランニングコストの安いエアホーンタンクにフルオートガスガンユーザーは皆飛び付きました。
しかしエアホーンタンクは当然ですが、入っている圧力が直結でそのまま出てくると言う代物です。
圧力規制の最初はレギュレーターのないエアホーン用タンクの直結を規制する意味で8気圧位の規制でした。
今から考えると確かにとんでもない圧力ですが、まあ、初期のフルオートガスガンなんて、ガス垂れ流しでたいした性能では無かったんですけどね。
ましてや直結の場合、撃てば撃つほど圧力は下がり威力もサイクルも落ちる訳ですし、圧力が安定しない状態ではセッティングもへったくれもあったものではありません。
極悪ハイパワーの象徴のように言われるJACやアサヒのBV式ガスガン(当時はそんな呼び方は一般的では無かったですけど、以後便利なのでこの表記を使います)ですが、エアタンク登場当初は、それほど恐れられてはいませんでした。
最も脅威だったのはコクサイのセミオートM16。
外観は先代スーパーウェポン使い回しながら、唯一のM16の実用的ガスガンでした。
当時としては命中精度が高く、スナイパーライフルとしても割と長い期間活躍した隠れた名銃であります。
他にも、MGC93R等やWAのAR7等。
当初はフルオートの為に使用されたであろうエアタンクは、高圧で安定した高い威力を発揮できるので、セミオートガスガンにも使用されました。
SS9に比べても圧力次第では簡単に強力に出来るので恐れらる様になり、エアタンク登場当初に、むしろ高威力で槍玉に上げられる事が多かったのはこちらの方だったのです。
恐らく、当時としてはSS9系と公平に同等の威力にしようと言う事で8気圧ぐらいと決めたのではなかったかと思います。
当初は圧力を落とす為の可変レギュレーターは高価な為、取り付けに反発もありましたが、レギュレーター装着した方が安定した性能が出せると言う事で結局あっと言う間に普及します。
と言うか、フルオートガスガンはレギュレーター付きになってようやく、まともな性能になったと言っても良い位です。
その後エアガン用タンクとして発売されたニッケンのタンクは固定レギュレーターが標準装備されていたのですが、可変レギュレーターに交換したり、レギュレーターの圧力が高くなるように改造するのは当たり前のように行われていました。
先行して普及していたのが可変レギュレーターで、高圧設定であったので、それに合わせる為ですが、当時のフルオートガスガンはメーカー出荷状態の出来が悪く、製品のバラツキもあって箱出しで低圧作動が出来ない物が結構あったのも、これらの改造を当初から否定出来なかった理由の一つでした。
JAC、アサヒのBV式ガスガンは正常作動には5気圧以上必要だった物が多く、圧力規制は長く5~6気圧が下限だった気がします。
また、箱出しのできの悪さ故に適正にチューニングした物との性能差が大きく、チューニングノウハウの有無による格差も問題でした。
実際、撃ち合って威力が違い過ぎるので、「レギュレーションを守っていないんだろう」と言う疑心暗鬼が生まれ、チェックが甘い事もあり安易に圧力を上げる人も居たようです。
このへんの事情が現在に続く、「外部ソース=インチキし易い」のイメージ定着につながったのではないかと思います。
少し後の話にはなりますが、後発で低価格商品だったマルゼンの製品のほうが、同じBV式ガスガンながら低圧ではむしろ最初から調子が良いと言う事もあり、低圧縛りのゲームでは多く見かけました。
低予算でサバゲが始められるので低圧ゲームは新規参加者も少なくはなかったと思います。
逆に高圧縛りだと、どうしても高級品を揃えなければ厳しいし、エア消費量も多いのでエアタンクもより大容量の物が必要、(スキューバ用タンクを流用するケースもありました)エア充填にも時間がかかりゲーム数が少なくなりがち、と言う事でコアな人達しか居なくなり、人数を減らして行きました。
話は少し横道に反れますが、エアタンク登場当初は個人で空気入れを持参、エア充填するのが当たり前だったのですか、インターバルに人力で空気を入れるのはゲーム以上に重労働、時間もかかりました。
1日で4ゲームしか出来なかった、なんて事もあった程です。
後にチーム単位や主催者がエンジンコンプレッサー等を持ち込むケースが多く見られる様になりましたが、エアタンク使用者が増えると充填待ちに時間を取られる様になり、やはりインターバルが長くなりがちになりました。
待ち時間が長くなるのは嫌だ、ゲーム数を増やしたいと言う参加者の希望もあり、インターバルを短縮する必要からエアの消費を抑える為、レギュレーションで圧力を低くする事が受け入れられ易かった、と言う側面もある様に思います。
外部ソースガスガンでのゲームも末期になると、トイテックのキャリコやP90等、高圧対応やパワーアップが難しい銃も登場してきます。
それまでフルオートガスガンの主流だったBV式に比べて多弾化され、低圧で安定した作動、ガス消費が少ない、値段も安かった等々メリットもありましたが、低圧レギュレーションがある程度普及していなければ受け入れられ、使用者が増える事は無かったでしょう。
BVガスガンの「リコイル」と言うのに相応しい反動と派手な発射音の愛好家は根強く存在しましたし、強力なエアガンでスリルを楽しむと言う趣向の人達も確かに居ました。
自然発生、寄り合いでゲームが開催されていた所がほとんどだったという事情でレギュレーションの不徹底、あるいは無制限に近いゲームは2008年の法規制施行まで存在してはいましたが、1990年頃、電動ガン登場の頃には低圧、低威力のレギュレーションでのゲームがある程度定着していた様に思います。
くどいですけど、まだ続きます。
2013年11月06日
おっさんゲーマーの回想録(3)
ここで、部屋で発掘した古い雑誌を参照してみます。

1987年発売、当時アームズマガジンはまだ創刊されて無かったので、ホビージャパン誌の別冊です。
広告から、既にJACのスターリン、M60や、UZI等が発売されている事が解ります。
「極悪パワー」「暗黒時代」と呼ばれる時代を既に迎えている訳ですが、記事中にも広告にもエアタンクの姿はありません。
当時唯一の業界団体であるASGKの影響力は大きく、記事や広告に自主規制に反する記載をする事は制限されていたからです。

興味深いのは、記事中に既に「極悪パワー」の記述があり、ハイパワー化の懸念があった事が伺え、その中に僅かに「高圧ボンベ使用」が批判的に触れられています。
雑誌媒体の記事がサバゲの状況とかけ離れてしまい、記録として残り難かったのが、当時の状況を不透明にしてしまっている、と言うのも「暗黒時代」等と言われてしまう原因の一つでしょう。
じゃあ実際、「サバゲの黒歴史」とさえ言われる事もあるこの当時のゲームは一体どんな物だったのか・・・・・。?
その当事、現在の一般的な弾の倍近い重量の弾を、外装式の高圧エアタンクの圧力で飛ばし、相手に勝つ為、更なるパワーアップに誰もが血道を上げ、パワー競争の結果ゲームでは怪我人が続出、流血沙汰も度々、新規参加者は減り、嫌気が差した人々が去り、ゲーマーが激減した・・・・・
そんなイメージで語られる事が多いと思いますが、結論から言ってしまうと、今と変わらず、撃ち合いを楽しんでいた、だけです。
自分の主観によりますが、当事と言えども怪我で流血となれば騒ぎにもなりますし、治療も必要。
ゲームが中断してしまう事もあり、その度に撃った方も撃たれた方も、周りもイヤな雰囲気になり楽しくない気持ちになるのが常でした。
当然、威力を規制しようよと言う話は早い時期から自然と出てきて、不完全ながらもパワー規制が定められるような流れになりました。
「レギュレーション」と言う言葉が使われ始めたのは当時大ブームだったF1GPの影響と記憶していますから、恐らくこの本より後の1988~89頃と思われますが、それ以前に何かしら威力を規制する事は結構当たり前になっていたのではないかと思います。
昔のゲーマーも今と変わらず、撃ち合いを楽しむためにサバゲをやっていたのであって、痛がる相手を見て喜ぶとか、撃たれて気持ち良くなるとかの特殊な精神状態や風変わりな趣向(まあサバゲ自体が風変わりな趣向と言ってしまえばそれまでですが)を持ってた訳ではないですよ、と言う事です。
とは言え、規制の多くは弾速の明確な制限ではなかったですね。
弾速計は現在に比べるとずっと高価でしたので、殆ど普及していませんでした。
なので、威力で規制する場合「アルミ缶接射で両面貫通程度まで」みたいな曖昧な物でしたし、ゲームの成立状況からやむを得ないとも言えますが徹底もされず、事前に調整してくる目安的な規制でしかない場合が殆どでした。
(普段雑誌の類いを買わない俺がこの本を買ったのは、威力と初速、アルミ缶の貫通の目安が表になっていて、当時威力規制を考える上で参考になるから、でした)
また、有料フィールドもまだ無い時代ですから、レギュレーションを徹底させる事は結構難しかったのも覚えています。
ゲーム開始前に参加人数分の同じアルミ缶をキレイな常態で用意しとく、と言うだけで現実的ではないですね(笑)
試しにやってみた事はありますが、毎回となると大変です。
で、明確な基準として当時の主流だった外部パワーソースのエア圧力や、使用弾の重さを制限する事になった訳です。
続く。

1987年発売、当時アームズマガジンはまだ創刊されて無かったので、ホビージャパン誌の別冊です。
広告から、既にJACのスターリン、M60や、UZI等が発売されている事が解ります。
「極悪パワー」「暗黒時代」と呼ばれる時代を既に迎えている訳ですが、記事中にも広告にもエアタンクの姿はありません。
当時唯一の業界団体であるASGKの影響力は大きく、記事や広告に自主規制に反する記載をする事は制限されていたからです。

興味深いのは、記事中に既に「極悪パワー」の記述があり、ハイパワー化の懸念があった事が伺え、その中に僅かに「高圧ボンベ使用」が批判的に触れられています。
雑誌媒体の記事がサバゲの状況とかけ離れてしまい、記録として残り難かったのが、当時の状況を不透明にしてしまっている、と言うのも「暗黒時代」等と言われてしまう原因の一つでしょう。
じゃあ実際、「サバゲの黒歴史」とさえ言われる事もあるこの当時のゲームは一体どんな物だったのか・・・・・。?
その当事、現在の一般的な弾の倍近い重量の弾を、外装式の高圧エアタンクの圧力で飛ばし、相手に勝つ為、更なるパワーアップに誰もが血道を上げ、パワー競争の結果ゲームでは怪我人が続出、流血沙汰も度々、新規参加者は減り、嫌気が差した人々が去り、ゲーマーが激減した・・・・・
そんなイメージで語られる事が多いと思いますが、結論から言ってしまうと、今と変わらず、撃ち合いを楽しんでいた、だけです。
自分の主観によりますが、当事と言えども怪我で流血となれば騒ぎにもなりますし、治療も必要。
ゲームが中断してしまう事もあり、その度に撃った方も撃たれた方も、周りもイヤな雰囲気になり楽しくない気持ちになるのが常でした。
当然、威力を規制しようよと言う話は早い時期から自然と出てきて、不完全ながらもパワー規制が定められるような流れになりました。
「レギュレーション」と言う言葉が使われ始めたのは当時大ブームだったF1GPの影響と記憶していますから、恐らくこの本より後の1988~89頃と思われますが、それ以前に何かしら威力を規制する事は結構当たり前になっていたのではないかと思います。
昔のゲーマーも今と変わらず、撃ち合いを楽しむためにサバゲをやっていたのであって、痛がる相手を見て喜ぶとか、撃たれて気持ち良くなるとかの特殊な精神状態や風変わりな趣向(まあサバゲ自体が風変わりな趣向と言ってしまえばそれまでですが)を持ってた訳ではないですよ、と言う事です。
とは言え、規制の多くは弾速の明確な制限ではなかったですね。
弾速計は現在に比べるとずっと高価でしたので、殆ど普及していませんでした。
なので、威力で規制する場合「アルミ缶接射で両面貫通程度まで」みたいな曖昧な物でしたし、ゲームの成立状況からやむを得ないとも言えますが徹底もされず、事前に調整してくる目安的な規制でしかない場合が殆どでした。
(普段雑誌の類いを買わない俺がこの本を買ったのは、威力と初速、アルミ缶の貫通の目安が表になっていて、当時威力規制を考える上で参考になるから、でした)
また、有料フィールドもまだ無い時代ですから、レギュレーションを徹底させる事は結構難しかったのも覚えています。
ゲーム開始前に参加人数分の同じアルミ缶をキレイな常態で用意しとく、と言うだけで現実的ではないですね(笑)
試しにやってみた事はありますが、毎回となると大変です。
で、明確な基準として当時の主流だった外部パワーソースのエア圧力や、使用弾の重さを制限する事になった訳です。
続く。
2013年11月01日
おっさんゲーマーの回想録(2)
俺が上京して本格的なサバゲを始めた当時は、スプリング式エアガンが主流で、しかも自作ケースレス化が殆どでした。
良く使われていたのはマルゼンのKG9やミニウージー、ファルコントーイのMP5SD3、タカトク(この時期、残念ながら倒産してしまいますが)SS9やマスダヤミニットマン10などなど。
マルゼン製は丈夫で威力も強く(とは言っても現在のエアガンと同程度以下ですが)人気が高かったですね~。
CSC(ケースレスシステムカートリッジ)なんて商品もあり、これはカートリッジ形状でリム部分に可動式のノズルが組み込まれ、カートの横っつらに空いた穴からBB弾を給弾、容易にケースレス化するためのキットなのですが、チャンバーに挿入、接着固定、CSCの穴に合わせてチャンバーと本体に穴あけて、別売のチューブ形状のケースレスマガジンを装着して使用する物でした。
これらケースレスカスタム用のパーツと、レピーター(ポンプアクション)化パーツ、それと強化スプリングが当初の人気のカスタムパーツでした。
とは言え、当初は殆どは気密性が悪く、威力も精度も知れた物でした。
当時のエアガンの殆どは主要部品がプラスチック、本体もモナカ構造で強度もなく、極端に強力なスプリングを使えば簡単に壊れてしまいました。
唯一、最後まで生き残ったのはSS9系くらいでしょうか。
タカトク倒産後は現在のマルコシに生産が引き継がれ、後にケースレス化。
並外れたシリンダー容量とシンプルで丈夫な構造から威力を上げても壊れ難く、カスタムパーツも豊富だった事から、APS2発売までボルトアクションライフルの代表の座にあり続けました。
それ故に極悪パワーの代名詞としてある意味有名になってしまいましたが、当時としては最も使えるエアガンの一つで、俺も使ってた時期が長かったです。
フルオートガスガン登場直前には、かなり過激な威力までチューンアップノウハウが確立していたと思います。
とは言えパワーのキモは結局スプリング頼み。
手でコッキング出来ないなんてトンデモな代物も結局連射出来ないので驚異にはならず、サバゲでは速射性能の優れたレピーター(ポンプアクション)エアガンと共存していました。
モデルガンメーカーの参入も相次ぎ、マルシンのM1/レンジャーカービン、ハドソンのグリースガン、コクサイのスーパーウェポンシリーズ、M700とM16、等。
エアガンに否定的だったMGCすら時勢には逆らえませんでした。
初のエアガンは革新的なケースレスガスガン。
93Rはその後ロングセラーとなる名機で、ゲームでも良く使われていました。
WAもAR7をガスガン化しています。
モデルガン並みのリアルな外観は、この頃からエアガンの標準になって行きました。
とはいえ今では当たり前にある人気銃M16すら、ラインナップにはまだ殆ど無く、サバゲフィールドではケースレス化による外装マガジンやレピーターカスタムが主力ですからリアルさとか、何とか装備コスプレ系とかには全くほど遠い状況でした。
今はホントに良い時代だと思いますよ~。
JACから日本初のフルオートガスガン、バトルマスターが発売となるのもこの頃ですが、初期型は高価な割にネジ込み式マガジンの使い勝手の悪さと、フロンガスではまともに作動しないしコストも高過ぎ、等々評価は低く、あまり普及しませんでした。
フルオートガスガンが増えるのは、ワンタッチ着脱マガジンを搭載したスターリンの登場以降です。
フロンガスの気化効率を上げるブースター(ボンベと空ボンベを数本、ホースでつないだ物)から、エアタンク使用へと移り変わり、このエアタンクとガスガンの組合せがパワー競争を一気に加速させました。
「極悪パワー時代」「暗黒時代」等と呼ばれる様な時代の幕開けとなる訳です。
続く。
良く使われていたのはマルゼンのKG9やミニウージー、ファルコントーイのMP5SD3、タカトク(この時期、残念ながら倒産してしまいますが)SS9やマスダヤミニットマン10などなど。
マルゼン製は丈夫で威力も強く(とは言っても現在のエアガンと同程度以下ですが)人気が高かったですね~。
CSC(ケースレスシステムカートリッジ)なんて商品もあり、これはカートリッジ形状でリム部分に可動式のノズルが組み込まれ、カートの横っつらに空いた穴からBB弾を給弾、容易にケースレス化するためのキットなのですが、チャンバーに挿入、接着固定、CSCの穴に合わせてチャンバーと本体に穴あけて、別売のチューブ形状のケースレスマガジンを装着して使用する物でした。
これらケースレスカスタム用のパーツと、レピーター(ポンプアクション)化パーツ、それと強化スプリングが当初の人気のカスタムパーツでした。
とは言え、当初は殆どは気密性が悪く、威力も精度も知れた物でした。
当時のエアガンの殆どは主要部品がプラスチック、本体もモナカ構造で強度もなく、極端に強力なスプリングを使えば簡単に壊れてしまいました。
唯一、最後まで生き残ったのはSS9系くらいでしょうか。
タカトク倒産後は現在のマルコシに生産が引き継がれ、後にケースレス化。
並外れたシリンダー容量とシンプルで丈夫な構造から威力を上げても壊れ難く、カスタムパーツも豊富だった事から、APS2発売までボルトアクションライフルの代表の座にあり続けました。
それ故に極悪パワーの代名詞としてある意味有名になってしまいましたが、当時としては最も使えるエアガンの一つで、俺も使ってた時期が長かったです。
フルオートガスガン登場直前には、かなり過激な威力までチューンアップノウハウが確立していたと思います。
とは言えパワーのキモは結局スプリング頼み。
手でコッキング出来ないなんてトンデモな代物も結局連射出来ないので驚異にはならず、サバゲでは速射性能の優れたレピーター(ポンプアクション)エアガンと共存していました。
モデルガンメーカーの参入も相次ぎ、マルシンのM1/レンジャーカービン、ハドソンのグリースガン、コクサイのスーパーウェポンシリーズ、M700とM16、等。
エアガンに否定的だったMGCすら時勢には逆らえませんでした。
初のエアガンは革新的なケースレスガスガン。
93Rはその後ロングセラーとなる名機で、ゲームでも良く使われていました。
WAもAR7をガスガン化しています。
モデルガン並みのリアルな外観は、この頃からエアガンの標準になって行きました。
とはいえ今では当たり前にある人気銃M16すら、ラインナップにはまだ殆ど無く、サバゲフィールドではケースレス化による外装マガジンやレピーターカスタムが主力ですからリアルさとか、何とか装備コスプレ系とかには全くほど遠い状況でした。
今はホントに良い時代だと思いますよ~。
JACから日本初のフルオートガスガン、バトルマスターが発売となるのもこの頃ですが、初期型は高価な割にネジ込み式マガジンの使い勝手の悪さと、フロンガスではまともに作動しないしコストも高過ぎ、等々評価は低く、あまり普及しませんでした。
フルオートガスガンが増えるのは、ワンタッチ着脱マガジンを搭載したスターリンの登場以降です。
フロンガスの気化効率を上げるブースター(ボンベと空ボンベを数本、ホースでつないだ物)から、エアタンク使用へと移り変わり、このエアタンクとガスガンの組合せがパワー競争を一気に加速させました。
「極悪パワー時代」「暗黒時代」等と呼ばれる様な時代の幕開けとなる訳です。
続く。
2013年10月31日
おっさんゲーマーの回想録(1)
またしばらくはゲームにも参加出来そうにもないし、マルイガスブロG18Cの盆栽遊びはお小遣い使いすぎてしまって小休止~、と言う事でブログ更新のフレッシュなネタが無い!!
まあ別にネタが無いなら無理に更新する事も無いのですが、自分なりのサバゲ史的な物をアップしてみようかと思いついた訳です。
ここんとこ仕事の合間とかに書き貯めた駄文を編集した物で、何でそんな物を書き始めたかと言うと、一つは引っ越しで荷物整理してたら、古いエアガンの本が出てきて当時を懐かしむ機会があった事。
雑誌の類は殆ど買わないし、取っておく事もないのでこの手の物が残っているのは俺としては珍しいのですが。
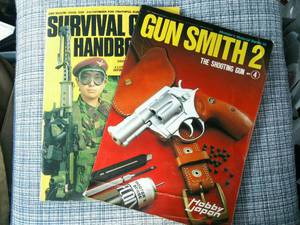
もう一つは、ちょっと前になりますがアニメ「C3部」の公式HPのサバゲ講座を読んで以来、ちょっと引っ掛かる物を感じていたからです。
あるいはウィキペディアのサバゲの項を見ても似たような事が書いてあるのですが「極悪ハイパワー暗黒時代」と言う様な表記に対する違和感です。
・・・・・何か、暗鬱とした雰囲気の中で皆が、薬中みたいに目の下にクマ作って取りつかれた様にゲームしてたみたいな印象になりませんかねぇ~?(笑)
ネットが普及する以前の事は情報が少なく、検索してもネガティブな断片的な個人的回想が僅かにヒットするだけ。
まるで冷戦時代の鉄のカーテンの向こう側の様に情報が遮断されているみたいですなぁ。
まあ、俺が思いつきで過疎ブログに書いた所でその状況に変化がある訳ではないのですが、少しは見てくれてる人もいるみたいなので、感じた事を書き残しておこうと思った訳です。
元来、自慢話や古参を鼻にかけて先輩風吹かすような真似は大嫌いなので、そういう内容にはならないようにしたいと思います。
また、あくまでも俺個人の周囲の事、俺が感じた事なので、同じ時代にゲームをしていた人でも「違う」と感じる人も居るかもしれません。
今みたいに情報伝達が早くない時代の事でもあり、ごく近くのフィールドで遊んでいても全く状況が違ったと感じる人も居ると思われますが、個人の主観と言う事でご了承下さい。
明らかな間違いがあったら、ご指摘頂けたら幸いであります。
えー、まず俺がサバゲにハマるキッカケから。
高校3年の時、後輩が部室に持ってきたエアガンに感動した為でした。
そのエアガンが、マルゼンのM59のクリーンヒッターカスタムと言う代物だった訳ですが詳細は省きます。
ちなみに、当時俺はバリバリのアニメ&プラモヲタクで、小遣いの殆どは主にガンプラにつぎ込まれていたのですが、ミリタリーや鉄砲も周辺情報として守備範囲ではありました。
当事俺が知っていたエアガンはツヅミ弾のオモチャっぽいやつで、性能も外観も屋台の射的銃と変わらない物でした。
対して、件のM59はまるでモデルガンのようなリアルさと質感を持っていました。
今から思うと「リアルな外観(笑)迫力のブローバック(笑)と排莢(笑)」なんですが、当時はマジでノックアウトでした。
しかしそれ以上にノックアウトだったのが初めて見た「BB弾」とその驚異の命中精度(あくまでも当時としては、ですよ)でした。
「5m先のマッチ箱を、百発百中(やや誇張してます)弾き飛ばせる!」
当時、BB弾仕様のエアガンが相次いで発売されていた時期だったのですが、それ以前の主流だったツヅミ弾は、比重が軽く空気抵抗による減速が大きく、遠くまでまっすぐ飛ぶ事はありませんでした。
しかもメーカーによって大きさや形、材質がバラバラで、ほぼ専用弾と言って良い状態なのです。
都会の大きなショップならともかく、俺の住んでた田舎町のオモチャ屋では、極端な話、付属の弾が無くなると入手困難、使用不能になる可能性が高い物と言う認識でした。
BB弾と言う共通規格弾を得る事で、性能向上した事はもちろんですが、個別に存在しているオモチャの鉄砲達から「エアガン」と言う大きなカテゴリーに一歩進化したと言って良いでしょう。
そして、その後輩が後に持って来た雑誌にはエアガンを使った「サバイバルゲーム」と言う目新しい遊びが紹介されていて、俺はすっかり興奮してしまった訳です。
早速友人や弟たちと近所の神社やら田んぼでサバゲぽい事をやってみましたよ。
全員ゴーグル着用と言うルールが銀玉合戦と違って格好よいなあと思ってました(笑)
とは言えサバゲ専用ゴーグルなど田舎町で売ってる訳も無く、金物屋で買ってきた作業用やスキー用のではありましたが。
急速にエアガンにのめり込み、何丁か買って雑誌を読みあさり、少ない情報をかき集めカスタムに挑戦したりもしました。
エアガンの殆どがまだケース式で強化バネやケースレス多弾カスタム用のパーツ等々が流通し始めたばかり。
ほどなく進学で上京、住む場所を決めるのに何件かのエアガンショップを偵察、サバゲに力を入れていて感じが良かった某店のあるO田区に決めた程の熱の入れようだったのです。
この某店にはサバゲを中心に入り浸り、後にバイトを経て、最初の就職先にもなりました。
なので、俺の本格的サバゲ歴のスタートはこの某店近辺から始まる事になります。
世の中は後にバブルと言われる時代に入りつつあったのですが、エアガン、サハゲ業界も空前の好景気の影響で急速な発展をしたのかもしれませんなぁ。
続く。
まあ別にネタが無いなら無理に更新する事も無いのですが、自分なりのサバゲ史的な物をアップしてみようかと思いついた訳です。
ここんとこ仕事の合間とかに書き貯めた駄文を編集した物で、何でそんな物を書き始めたかと言うと、一つは引っ越しで荷物整理してたら、古いエアガンの本が出てきて当時を懐かしむ機会があった事。
雑誌の類は殆ど買わないし、取っておく事もないのでこの手の物が残っているのは俺としては珍しいのですが。
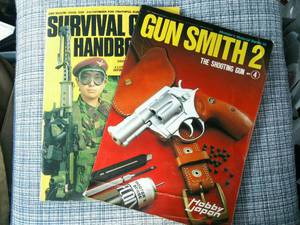
もう一つは、ちょっと前になりますがアニメ「C3部」の公式HPのサバゲ講座を読んで以来、ちょっと引っ掛かる物を感じていたからです。
あるいはウィキペディアのサバゲの項を見ても似たような事が書いてあるのですが「極悪ハイパワー暗黒時代」と言う様な表記に対する違和感です。
・・・・・何か、暗鬱とした雰囲気の中で皆が、薬中みたいに目の下にクマ作って取りつかれた様にゲームしてたみたいな印象になりませんかねぇ~?(笑)
ネットが普及する以前の事は情報が少なく、検索してもネガティブな断片的な個人的回想が僅かにヒットするだけ。
まるで冷戦時代の鉄のカーテンの向こう側の様に情報が遮断されているみたいですなぁ。
まあ、俺が思いつきで過疎ブログに書いた所でその状況に変化がある訳ではないのですが、少しは見てくれてる人もいるみたいなので、感じた事を書き残しておこうと思った訳です。
元来、自慢話や古参を鼻にかけて先輩風吹かすような真似は大嫌いなので、そういう内容にはならないようにしたいと思います。
また、あくまでも俺個人の周囲の事、俺が感じた事なので、同じ時代にゲームをしていた人でも「違う」と感じる人も居るかもしれません。
今みたいに情報伝達が早くない時代の事でもあり、ごく近くのフィールドで遊んでいても全く状況が違ったと感じる人も居ると思われますが、個人の主観と言う事でご了承下さい。
明らかな間違いがあったら、ご指摘頂けたら幸いであります。
えー、まず俺がサバゲにハマるキッカケから。
高校3年の時、後輩が部室に持ってきたエアガンに感動した為でした。
そのエアガンが、マルゼンのM59のクリーンヒッターカスタムと言う代物だった訳ですが詳細は省きます。
ちなみに、当時俺はバリバリのアニメ&プラモヲタクで、小遣いの殆どは主にガンプラにつぎ込まれていたのですが、ミリタリーや鉄砲も周辺情報として守備範囲ではありました。
当事俺が知っていたエアガンはツヅミ弾のオモチャっぽいやつで、性能も外観も屋台の射的銃と変わらない物でした。
対して、件のM59はまるでモデルガンのようなリアルさと質感を持っていました。
今から思うと「リアルな外観(笑)迫力のブローバック(笑)と排莢(笑)」なんですが、当時はマジでノックアウトでした。
しかしそれ以上にノックアウトだったのが初めて見た「BB弾」とその驚異の命中精度(あくまでも当時としては、ですよ)でした。
「5m先のマッチ箱を、百発百中(やや誇張してます)弾き飛ばせる!」
当時、BB弾仕様のエアガンが相次いで発売されていた時期だったのですが、それ以前の主流だったツヅミ弾は、比重が軽く空気抵抗による減速が大きく、遠くまでまっすぐ飛ぶ事はありませんでした。
しかもメーカーによって大きさや形、材質がバラバラで、ほぼ専用弾と言って良い状態なのです。
都会の大きなショップならともかく、俺の住んでた田舎町のオモチャ屋では、極端な話、付属の弾が無くなると入手困難、使用不能になる可能性が高い物と言う認識でした。
BB弾と言う共通規格弾を得る事で、性能向上した事はもちろんですが、個別に存在しているオモチャの鉄砲達から「エアガン」と言う大きなカテゴリーに一歩進化したと言って良いでしょう。
そして、その後輩が後に持って来た雑誌にはエアガンを使った「サバイバルゲーム」と言う目新しい遊びが紹介されていて、俺はすっかり興奮してしまった訳です。
早速友人や弟たちと近所の神社やら田んぼでサバゲぽい事をやってみましたよ。
全員ゴーグル着用と言うルールが銀玉合戦と違って格好よいなあと思ってました(笑)
とは言えサバゲ専用ゴーグルなど田舎町で売ってる訳も無く、金物屋で買ってきた作業用やスキー用のではありましたが。
急速にエアガンにのめり込み、何丁か買って雑誌を読みあさり、少ない情報をかき集めカスタムに挑戦したりもしました。
エアガンの殆どがまだケース式で強化バネやケースレス多弾カスタム用のパーツ等々が流通し始めたばかり。
ほどなく進学で上京、住む場所を決めるのに何件かのエアガンショップを偵察、サバゲに力を入れていて感じが良かった某店のあるO田区に決めた程の熱の入れようだったのです。
この某店にはサバゲを中心に入り浸り、後にバイトを経て、最初の就職先にもなりました。
なので、俺の本格的サバゲ歴のスタートはこの某店近辺から始まる事になります。
世の中は後にバブルと言われる時代に入りつつあったのですが、エアガン、サハゲ業界も空前の好景気の影響で急速な発展をしたのかもしれませんなぁ。
続く。

